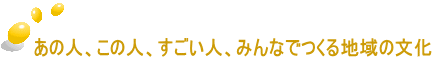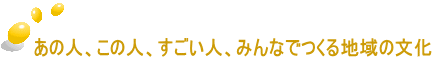|
【名前】10組・池田 順作
【作品題名】①「スバル」
【作品の解説】
スバルは「枕草子」に出てくる。今から千年も前に清少納言も見ていた。プレアデス星団ともいうが、和名が昂(すばる)。冬の晴れた空を見上げると、ちょうど頭上に見える。肉眼では7個の小さな星が宝石のように集まって見える。双眼鏡があれば、写真のように数十個見えて大変美しい。「すばる」は動詞では「統る」と書き、ものが集まって1つになること。
地球からの距離400光年、これは光の速さで400年かかる距離だ。つまり400年前(江戸時代初期)に出た光を、我々は今見ている。

|
 |
【名前】10組・池田 順作
【作品題名】②「アンドロメダ星雲」
【作品の解説】双眼鏡や望遠鏡で見ると雲に見える。そこで星雲という名がつくが、雲ではなく約2000億個の星の大集団だ。このような多数の星の集団を銀河という。我々の太陽系が属する銀河も、大きさも形もこのアンドロメダ銀河とよく似ている。 我々が夜空を見上げて見える星(この写真の星雲の周囲に点々と写っている多くの星たち)は、たいてい10~数百光年の距離にある我々の銀河内の星だが、アンドロメダ銀河は約230万光年の距離にある。サルから人類に進化しつつある頃の 230万年前の光が、ようやく今地球に届く、そんな遠い距離にある。和歌山県竜神スカイラインで撮影。

|
 |
【名前】10組・池田 順作
【作品題名】③「オリオン大星雲」
【作品の解説】
冬の夜空、3つ星がすぐ目につくオリオン座。その3つ星のすぐ下にある星雲だ。アンドロメダと違って、こちらは本当の星雲。肉眼でもぼんやり見える。その実態は、宇宙空間のガスが、近くの恒星の熟と光によって輝いている姿で、ここからやがて新しい星が生まれる。宇宙では絶えず新しい星が生まれ、古い星が死んでいく。我々の銀河系内にあり、距離1500光年、つまり日本に仏教が伝来した頃に出た光が今見えている。

|
 |
【名前】10組・池田 順作
【作品題名】④「ヘールボップ彗星」
【作品の解説】
一般に彗星はほとんどが氷、または 雪のかたまりで、熱に弱く、太陽に近づくと氷の一部が融けだして、水蒸気になり、それが我々には長い「しっぽ」として見える。写真は1997年の大彗星であるヘー ルボップ彗星で、3カ月以上肉眼で楽に観測できた。彗星核は直径 50kmという巨大なもの。太陽を回る公転周期は2530年。

|